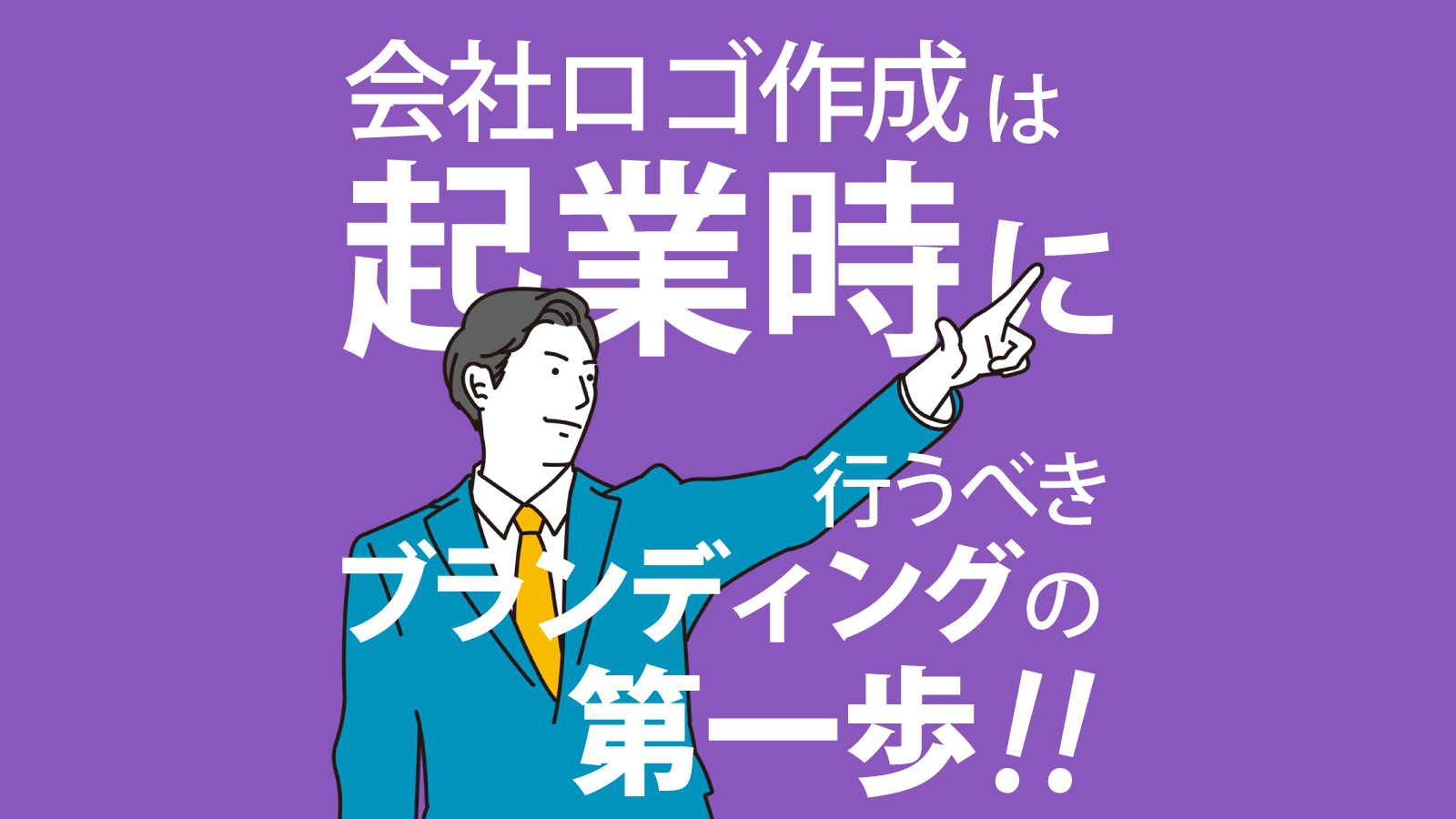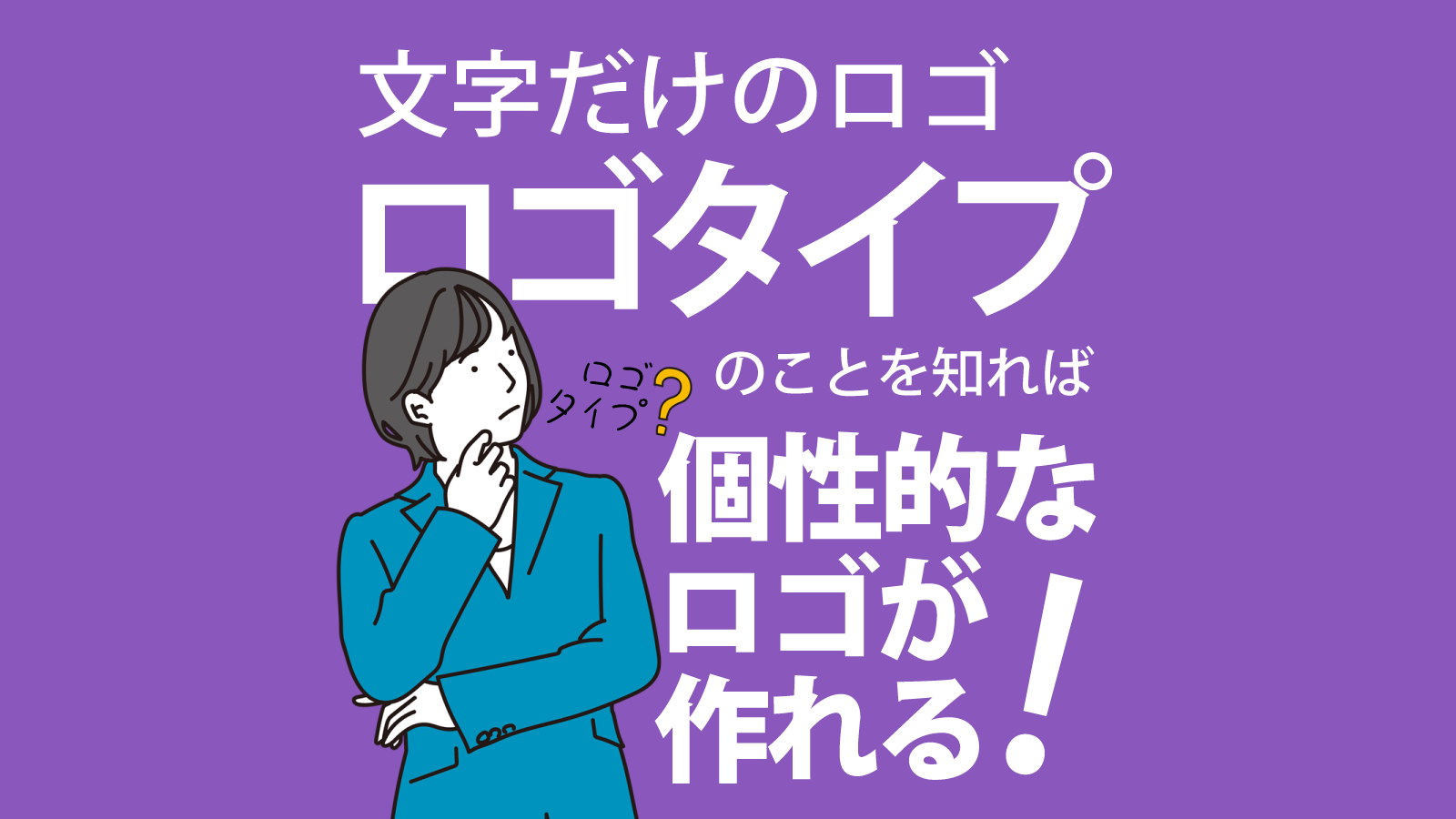ロゴ制作・ロゴデザインを依頼するならsynchlogo(シンクロゴ)
ロゴコラム
COLUMN

おしゃれなオリジナルロゴの作り方と事例紹介

カテゴリー
センスが求められる業種や、流行の商品やサービスを提供する業態では、ロゴをおしゃれなものにしたいと考えると思います。ロゴは会社やお店、商品やサービスの顔になる重要なブランディングツールですので、ロゴでも競合に負けないおしゃれなものを作りたいのではないでしょうか。ロゴのおしゃれさが足りないために機会損失するというのは避けたいところですよね。
そこでここではおしゃれなロゴを作りたい方に向けて、「おしゃれなロゴ作りの学習方法」「おしゃれなロゴの作り方5つのポイント」を紹介したいと思います。
また後半では、それらのポイントを押さえてsynchlogoが制作したおしゃれなロゴの制作事例10点もご紹介いたしますのでどうぞご覧ください。
【目次】
1.「おしゃれなロゴ」の定義
2.おしゃれなロゴが作れるようになるには
3.おしゃれなロゴの作り方5つのポイント
4.synchlogoで制作したおしゃれなロゴ事例10選
5.おわりに
1.「おしゃれなロゴ」の定義
おしゃれと感じるデザインは色々ある
一言におしゃれと言っても、何を「おしゃれ」と感じるかは人それぞれだと思います。ファッションにおいて、着る服の好みのジャンルが人によって違うように、ロゴでも「おしゃれ」と感じるデザインは色々あるはずです。ではどんな方向性のデザインがおしゃれと感じるかを、有名な企業やサービスのロゴ事例とともにいくつか挙げてみることにしましょう。
シンプルなデザイン
必要ない装飾などを排除し、伝えたいことをストレートに表現したデザインで、その潔さがおしゃれな雰囲気を醸し出しています。シンプルであるがゆえにごまかしが利かず、デザイナーの力量が最も試されるデザインだと言えるでしょう。

スマート・クールなデザイン
シャープな線や形、幾何学をベースにしたスマートでクールなデザインは、プロポーションなど形のバランスが重要となるデザインです。、会社や企業のロゴで最も用いられるデザインですので、社会的な信頼感や誠実さ、知的が伴うおしゃれさが求められます。

ポップ・かわいいデザイン
ポップなデザインやかわいいデザインは、若者・子ども向けの商品やサービス、またそれらを提供する会社やお店でよく用いられるデザインです。その時代の流行や話題になりそうな雰囲気であることが求められるため、ニーズしっかり調べた上でデザインすることが大切になります。

先進的・未来的なデザイン
各ジャンルにおいて、最先端のものを対象とする時に求められることが多いデザインです。社会におけるトレンドや最新の内容を踏まえた上で、適切な形でデザインに落とし込むことが重要になります。

トラディショナル・昔風のデザイン
過去に流行ったものや昔からあるものが「おしゃれ」とされることがあり、懐かしさや伝統をテーマとする時に必要とされるデザインです。あえて渋さや古めかしさが感じられるように、あえて既視感のあるデザインや、昔用いられたモチーフを取り入れるなどの工夫が必要になってきます。

ナチュラル・手作り感のあるデザイン
手作りやハンドメイド、自然志向のものを扱うなど、主に衣食住に関わる会社やお店、サービスなどで求められることがあるデザインです。自然界や環境を感じさせるモチーフや形を用いたり、あるいは手描きのようなテイストで作ったりするなど、やわらかさやストレスを感じさせないデザインとすることで「おしゃれ」が実現できます。

格式・気品のあるデザイン
ファッションにおけるハイブランドや高級レストラン、高級ホテルなど、非日常を演出する商品やお店、サービスで求められるデザインです。落ち着きある整った雰囲気から華やかで雅な雰囲気まで、幅広いデザインの方向性の中から適切な「おしゃれ」を選択しなければならないため、特にデザイナーのセンスが問われることになるでしょう。

個性的・ユニークなデザイン
あまり見たことがない、他にはなさそうな個性的なデザインや、ユニークなアイデアのデザインが「おしゃれ」とされることがあります。程度を間違えると妙なものになってしまうおそれもあるので、適切な塩梅でデザインに変わったことを取り入れるようにするとよいでしょう。

共通するのは「洗練されていること」
「おしゃれ」と感じるデザインは様々であることを紹介いたしましたが、共通する点を挙げますと、どのデザインも洗練されていなければ決しておしゃれには見えません。どんなにシンプルに作っても、どんなにかわいらしく作っても、本当にシンプルでかわいらしく出来ていなければ、それは決しておしゃれには見えないでしょう。詰まるところ、おしゃれなデザインとは洗練されていることが最低条件であると言えるのではないでしょうか。
2.おしゃれなロゴが作れるようになるには
自分が「おしゃれ」だと思う事例を集める
まずは自分がおしゃれだと思う事例を集めてみましょう。そうすることで、おしゃれだと思うデザインの傾向が上記のように整理できると思います。整理できた数だけおしゃれなデザインのバリエーションがあると考えてよいでしょう。その中から、内容に応じてどのパターンのデザインを適用するか考えればよいのです。こうして整理することで、デザインの引き出しを自分の中に作り上げることができます。そしてその引き出しがあればあるほど、より相応しいデザインを作ることができるようになるはずです。
最初は試しに真似して作ってみる
最初から思い通りにおしゃれなロゴを作るのは不可能です。頭の中で思い描いていても、実際形にするとなるとなかなか上手くは行かないものです。そこでまずは真似することから始めてみましょう。自分が作りたいと思っているおしゃれなロゴに近い事例を探し、それを参考にデザインしてみるのです。そうすることで、どこをどうしたらおしゃれに見えるのか、そのポイントが少しづつ掴めるようになると思います。
ただし、まるっきり同じものを作るのはやめた方が良いでしょう。それは、ただトレースをしただけで、おしゃれに見えるのかポイントが掴めないまま終わってしまうかもしれないからです。自分なりのオリジナリティが出るように、多少のアレンジは加えることが大切です。またあまり似せすぎると著作権や商標権に抵触する可能性もあるのでそのあたりも注意もするようにしましょう。
流行やトレンドをチェックする
自分がおしゃれだと思うデザインは上記2点で少しづつできるようになると思います。しかしそのデザインを他の人が見て「おしゃれ」と感じるとは限りません。デザインの評価はあくまで主観的で、詰まるところおしゃれと思うかどうかは個人の好みによるものなのです。
ではどうすれば他の人にも「おしゃれ」と思われるロゴが作れるのでしょうか。そのためにはおしゃれなデザインの流行やトレンドを追うようにしましょう。流行やトレンドは多くの人に受け入れられているという証拠なので、そのデザインを取り入れることで、他の人にもおしゃれと感じてもらえるロゴがきっと作れるようになるでしょう。
3.おしゃれなロゴの作り方5つのポイント
コンセプトをしっかり決める
オシャレなロゴを作る第一歩はまずコンセプトをしっかりと決めることです。対象の内容をしっかり吟味したうえで、どういった方向性のデザインにするかをまず言語化することが大切です。デザインの方向性がぼんやりしていたり、欲張って色んなデザインをあれこれ取り入れ過ぎたりすると、表現したいことが分かりづらい、ピントのボケたデザインになってしまいます。ですので、前述の「おしゃれと感じるデザインは色々ある」で示したように、どの方向性のデザインにするかしっかりと絞り込むことが重要です。
意味やメッセージよりも見た目を優先する
ロゴはよく、連想されるモチーフなどを使い、意味やメッセージをデザイン込め、オリジナリティある唯一無二のものを作ろうとします。しかしあまりそこにこだわり過ぎると、デザインの自由度がどうしても狭まってしまい、見た目のおしゃれさが損なわれてしまうこともしばしばあります。もちろん意味やメッセージを込めることは大切ですが、おしゃれなロゴを作るというテーマの方が大きい場合は、あまりそれにとらわれず、見た目の方を優先してデザインしていった方がよいでしょう。
たくさんの案を作り比較検討する
ひとつの案だけでは果たしてそのおしゃれさがきちんと出来上がっているか検証できないものです。コンセプトに沿ってさまざまな角度からデザイン案を作り、比較した上で最もおしゃれと感じる案を作り上げていくとよいでしょう。特に色については流行やトレンドも踏まえながら、複数色のバリエーションは必ず作り、その中から最適な色を絞り込んでいくようにしましょう。
競合や同種のロゴと並べてみて遜色ないか確認する
おしゃれなロゴが出来上がったと感じていても、本当にそれがおしゃれと感じてもらえるかどうかは、世に出してみないと分からないところもあります。なぜなら、競合や同種のロゴと比べてそのおしゃれさがもし劣っていたら、想像していたような効果が得られないかもしれないからです。ですのでロゴが出来上がった時は、必ず競合や同種のロゴと並べて見て、遜色ない仕上がりになっているかどうかを確認することが大切です。ブランディングは他者との競争ですから、ロゴでも負けないように意識を持つことが重要になります。
人に見てもらう
デザインの評価は主観的なもの、と前述しましたが、多くの人から見られるロゴがおしゃれに感じるかどうかを冷静に評価するために、一度人に見てもらうのも有効な手段です。デザインに精通した人に見てもらうのももちろん良いですが、できればデザインとは関係のない、ユーザー目線で見ることができる一般の方のほうがよい良いでしょう。「おしゃれ」という観点はとても感覚的なものなので、ロジックではなく、あくまで出来上がりの見た目でおしゃれと感じるかどうかを客観的に判断してもらうと良いと思います。
4.synchlogoで制作したおしゃれなロゴ事例10選
SAATHAUS(工務店による住宅ブランド)
「家が”きっかけ”になる」をコンセプトに、「家のたね」をモチーフにデザインしたロゴです。家づくりを身近で、親しみあるものに感じられるよう、まるっこく、かわいらしい雰囲気に仕上げました。トータルブランディングも意識し、サイトデザインとも呼応したデザインになっています。

Beans College(Web制作を学習するスクール&コミュニティ)
「スクールとコミュニティのあいだ」をコンセプトに、盾をモチーフにデザインしたロゴです。アカデミックな雰囲気は残しつつも、親しみやすいコミュニティであることが感じられるようにデザインしました。名前の由来である「豆」を連想させる芽の図形を取り入れるなどの工夫もしています。

株式会社リプカ(SNSマーケティング支援・WEB広告支援を行う会社)
「幸せが運ばれるつながり」をコンセプトに、なめらかに繋がれた社名が特徴のロゴタイプです。企業としての信頼感もありつつ、オリジナリティ溢れる雰囲気の字体によって、アイデンティティを強く感じさせるデザインに仕上げています。

interval studio(小売業の企画・デザイン集団)
「空白に新たな価値や物語を創る」をコンセプトに、屋号の由来である「間(=interval)」を「[ ](カッコ)」のモチーフによって表現したロゴです。モチーフ設定でユニークなヴィジュアルを作り出し、赤と黒の対比的なカラーリングで独創的な雰囲気を際立たせたデザインです。

Toiro(ヘアサロン)
「女性の輝き・華やかさ・煌びやかさ」をコンセプトに、花や宝石をイメージしてデザインしたロゴです。華やかさ、煌びやかさのあるデザインとしつつも、どこか包容力や、無から有を生み出す創造力も感じられるように仕上げております。

株式会社BREEZE(キャンプ場運営会社)
「森の中の家」をコンセプトに、自然や環境への敬意を表現したロゴです。一筆書きで描いたようなデザインで、やさしく親しみやすいヴィジュアルにしつつ、キャンプ場ならではの「自らの手で」という雰囲気も感じられるように仕上げております。

株式会社ミスターアザーズ(美容系IT企業)
「人に礼を尽くす」をコンセプトに、「相手に最大限敬意を払う、自分以外の人達を大切にする」という社名に込められた意味を表現したロゴです。脱帽した紳士の姿をそのままモチーフに用いるというユニークな表現方法でデザインいたしました。

株式会社DESTAJAPAN(資産コンサルティング会社)
「栄冠を経て、循環から辿り着いた到達点」をコンセプトに、最終的には資産があるべき場所へと辿り着くという考え方を表現したロゴです。イニシャルの「D」をベースに、資産の運用に成功した人が栄冠・栄光を掴んだイメージを「トロフィー」のモチーフでデザインしております。

mugi(ヘアサロン)
「踏まれて強く育つ」という、店名の由来をコンセプトにしたロゴです。その名称に相応しく、地平線から昇ってくる太陽のモチーフを取り入れ、コンセプトに相応し骨太な雰囲気がありつつも、ヘアサロンらしい繊細さも感じさせるデザインに仕上げました。

株式会社UNISEED HOLDINGS(マッチングやプロデュース事業を行う会社)
「未来へ成長していく価値の発見」をコンセプトに、グループ会社を統括する会社に相応しい雰囲気にデザインしました。イニシャルの「U」と「S」を組み合わせた図形をベースに、未来へ成長していく価値を象徴する「芽」を添えつつ、格式と遊び心が同居したようなデザインに仕上げました。

5.おわりに
一言におしゃれなロゴと言っても、なかなか奥深いことが分かって頂けたのではないかと思います。
通常のロゴの作り方とは異なる点もいくつかご紹介することができ、ロゴを作る側の方にも参考にして頂けたのではないでしょうか。
せっかく作るロゴですので、おしゃれなものになるように努めていきましょう!
お問い合わせ CONTACT
ロゴ制作に関するご相談など
お気軽にお問い合わせください。
フォームからのお問い合わせ